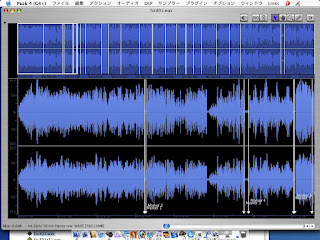前回テブノーの翻訳の最後に、iTunes StoreやAmazonで検索をかける話をした。私はその時、フォルクローレを演奏するグループはほとんどが"El Condor Pasa"を演奏しているから、50曲ぐらいヒットするのではないか程度に考えていたのだ。iTunes Storeで"El Condor Pasa"で検索をかけてみた。ついでに「全てをみる」のボタンを押したら、なんと1200もヒットしてしているのだ。アルバム名が"El Condor Pasa"になっていて、実際は別の曲の場合もあるから、実際はその2/3と見積もっても800もあることになる。フォルクローレのグループだけでなく、その他の楽器や、歌もある、これほど幅広く演奏されている曲だとは思わなかった。(Amazonでも同じ程度ヒットする)
ジャンルもLatino ポップ、ワールド、サウンドトラック、ヴォーカル、ビッグバンド、New Age,イージーリスニング、・・なんでもありだ。
楽器も ケーナや笛類だけではなく、金管楽器、サキソホーン、ヴァイオリン、 ジャズボーカル、朝丘雪路の歌まで見つけた。
それぞれ試聴出来るから少しずつ聴いてみるのも楽しい。MP3のダウンロードシステムならではの楽しみだろう。CD購入時代には考えられなかったことだ。 一曲が150〜200円程度だから、コレクションすることも出来る。本来はそれぞれのアルバムに加えられた一曲にすぎなかった曲でもこのように集めてみるとそれなりの意味を持ってくる。
iTuneストアでもAmazonでもそれぞれプリペイドカードがあるので、ダウンロードも安心して出来る。
少し気になった曲を挙げてみると、
フォルクローレ系では、どのグループも色々工夫して楽しませてくれる。ケーナに絞って考えると、オラルテ、テブノー、だろうか?テブノーは、テクニシャンぶりを発揮し、オラルテは、ケーナをたっぷり歌わせている。
そして森山良子が丁寧に歌いこんでいる。バックも出しゃばることなく決まっている。ケーナも歌える楽器だが、人間の声には かなわないと感じてしまう。
フォルクローレとして通常演奏される雰囲気とはずいぶんかけ離れている。
しかし 作者ロブレスが最初に作曲したのは、「コンドル・カンキ」という民族独立のために戦った英雄の音楽劇の序曲の一部だったそうだから、ロブレスの脳裏に壮大なオーケストラの響きも浮かんでいたかも知れない。
これだけ多岐に渡って演奏される曲はそんなにあるわけではないだろう。
かの名曲 J.S.Bachの管弦楽組曲第3番のAir(通称G線上のアリア)に匹敵するのではないだろうか。
ぜひEl Condor Pasaの森をさまよって見ることをお勧めする。